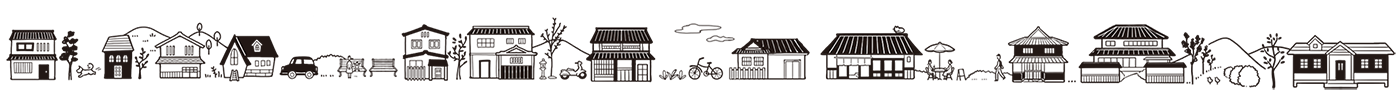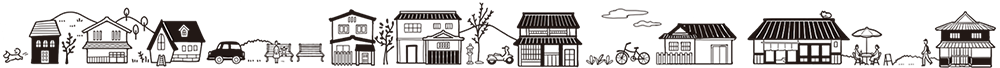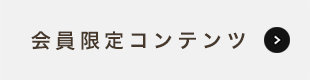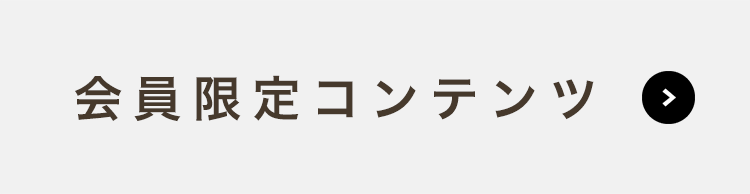続・林芙美子記念館に行ってきました
今回も引き続き林芙美子記念館レポです。
前回はこちら。

メインの縁側の左側はこのように、母屋から通路を挟んでアトリエへの視線が抜けます。
こういうのが古民家の醍醐味なんですよ。
うちも母屋から渡り廊下が見えるし、風呂から縁側にまで視線が通るんですけど、誰がどこにいるか、というのが視覚的に分かるということの気持ちよさ。
壁に囲われた「家」という抽象的な空間ではなく、ただ屋根があって、壁があって、床がある、その中に自分は暮らしてるんだという実感みたいなもの。
僕はそういうものが得られる暮らしをしたかったんです。
が、
そういう理屈は頭で考えるもんじゃなくて感じるものだから、べつにそんなこと考えてなくてもこの写真見た瞬間に「あ、なんかステキ」って思えるところがステキですね。
ただ一点僕的にステキじゃないところがあります。
それはこのテカテカの床。
これ最初からテカテカしてたのか? いやそんなわけはない、芙美子はそういうことしない、と思ってボランティアの方に訊いてみたらやっぱり後から塗られたそうです。
塗んなや。

小間。
ここにもブルーの差し色が効いてますが、説明を読むと「ひき合わせたくない客がぶつかると、客間としても使われました」とのこと。
良い。
そういうの好き。
当時はスマホが無いからいきなり自宅に凸が普通で、それゆえにバッティングすることも多かったのだろうと推測。
江戸時代の話とか読んでると、思わぬ藩士が鉢合わせたりして、そこから生まれる物語(殺傷事件とかな)もたくさんあっただろうなあと思いますよ。
それにしてもここから読み取れるのはやはり「客」という要素。
「客間」ですよ皆さん。
皆さんの家に「客間」ってありますか?
ないよね。
あるわけないよね。なんで客のためにわざわざ部屋を一個潰さんとあかんねんと。
そんな余裕あったら趣味の部屋にするかウォークインクローゼットにしますわと。
それが現代人の普通の感覚。
ですが、当時は「客」というものを非常に重視した。
うちの古民家だって自分たちが使う部屋は狭くて縁側もなく、反対に客間が廻り縁、床の間、書院を備えた一番豪華なつくりになってますが、古民家に住むと部屋がいっぱいあるので客間を持てるというのも一つの面白いところです。
そういう【プライベートではない】空間が自分の家に一つあると、何か、生活がシャキッとするんですよ。
家の中に小さい外部を持つということは、客を大事にし、自分を律するという、日本人の美学に通じるところでもある。
他者を、社会を重んじるからこそ、日本人は列になって電車をきちんと待つし、財布を落としても届けてくれたりするんですよね。
家の内部空間が100%自分のものに変わったとしても、そういうところは大事にしていきたいもんです。

こちらが玄関。
この玄関はもうパッと見てモダニズム建築ですね。
こういう建具とか照明とかのパーツじゃなくて、もっと細部のレベル(例えば入隅が大壁とか)で融合した和洋折衷デザインが素晴らしい。
玄関のデザインって難しいですよ。うちも玄関ほんと悩んだ。

玄関内部。
このように下駄箱と取り次ぎの間の間にちょっとした通路があり、それが縁側に直接繋がっています。
こういうギミックめっちゃ興奮する。
どう繋がってるかは前回の記事の間取り図を見てみてください。
ようするにたぶん、日常的に使うプライベートな入り口と、客を通す正式な入り口を左右に分けたんだろうと思います。

玄関から中を覗いてみるとこうなってます。
差し色ブルーが効いてるねえ。オシャレだねえ。
それにこのコンパクト感が都会で数寄屋でいいよねえ。
あ、今さらですけど林芙美子記念館は基本的に家の中には入れないんですよ。数ヶ月に一度、特別公開があるので、中に入りたい人は事前に申し込む必要があります。
僕はふらっと立ち寄ったので外からこうして覗き込むだけでした。
まあそれでも充分勉強になったけども。
で、
この奥に何やら増築的な雰囲気を感じたので、ぐるっと外から回って覗いてみました。

うーーーーーん。
使用人室、とのことですが。
ほんまか?
これほんまに当時の状態?
床のテカテカは後で塗られたとして、この壁ほんまに最初からこれ?
内装にこうして天井から床まで板張りにするかしら。
何か理由あったのか、それとも後で張られたのか…
しかも木部全部にニス塗ってますよね。ニス塗らんと思うけど。ブツブツ…
と僕はあちこちで腕組みしてブツブツやってたら、ボランティアガイドさんに開口一番「建築関係の方ですか?」と声をかけられてしまい、思わず
「な、なぜそれを!?」
と言ってしまったんですが、そんなセリフを人生でリアルで使うことになるとは思わんかったですよ。
ちなみのその後の
「何をされてるんですか?」
「あ、いや、えっと、建築といっても古民家の……なんていうか、ホームページとか……」
「はあ」
「あの、デザインとか……作家とか……」
「はあ」
みたいなやりとりはもはや様式美。
だれか一言で済む僕の職業名考えてください……

はい。
ここが林芙美子が執筆していた書斎です。
もうほんと、新人作家としては畏れ多くてこれ以上覗けない神聖な空間でした。
たとえるならこの部屋は皆さんにとってのスタジオジブリの宮崎駿監督が絵コンテ描いてる的な部屋です。
遠方から合掌するレベルです。
無理。

こちらは蔵ですね。
大谷石。
大谷は僕も愛用してますが古民家にもモダンにもめちゃくちゃ相性いいですね。
石自体が柔らかくて表情が豊かで、木にも瓦にも合うんですよ。
ただ今使うとかなり高い。
大谷石予算が別に必要。
それでも無理して使う価値はあると僕は思います。

これは離れのアトリエの床の間。
床の間なんぼあんねん。
この家、一部屋に一つ、くらいのレベルでトコノマってます。
これも現代なら絶対収納スペースになってるよね。
でもね、こういう「何の実用性もない空間」ってステキじゃないですか?
僕が見聞きした範囲では、床の間を知らない若い方々がリノベでここにドレッサー置いたり冷蔵庫放り込んだりしてるみたいですが、そうじゃねえんだ。
そうじゃねえんだよなあ。
「おいしくなって新登場!」とか「食べやすいサイズでご提供」とかいくら言っても値上げは値上げであるように、床の間もどこまでいってもやっぱり床の間なんですよ。
この空間は触っちゃだめですよ。
ここにジャストフィットすぎる大型液晶テレビ置きたい気持ちはめちゃくちゃ分かるけども、それならせめてプロジェクターにしようぜと、僕は思います。

はい。
以上、そんな感じで二回に分けてレポートしました林芙美子記念館、いかがだったでしょうか。
この家はただ東京で珍しく焼け残った古民家、というのではなく、当時を代表する建築家と作家がコラボしてつくりあげた「住宅」の名建築でした。
住宅だけに、あちこちに古民家リノベーションの今すぐ使えるヒントがあると思います。
関東在住の方はもちろん、遠方の方も、何かのついでにぜひ足を運んでみてくださいね。
あと文学好きは芙美子作品読んでから行ってみるといいよ!
おわり。