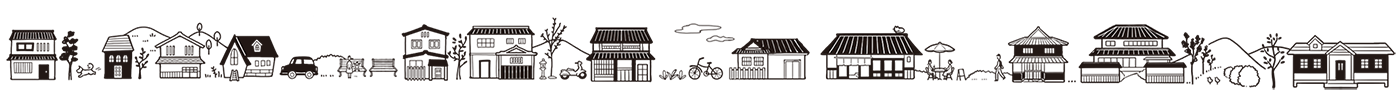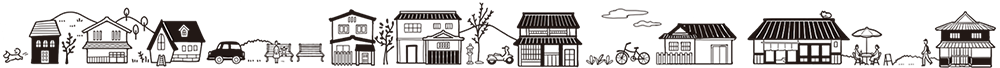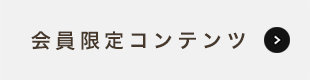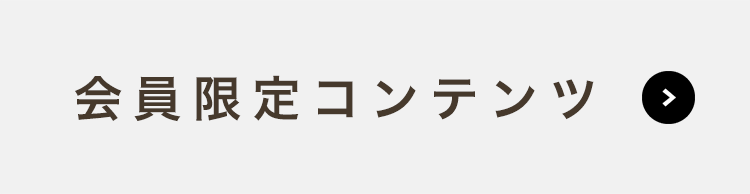能登半島地震レポート・その2
はい。前回に続き、今回も能登半島地震のレポートです。
前回の記事はこちら。
ということで前日入りしたその翌日、朝から一棟目の調査対象の家屋へと車を走らせました。
一日のスケジュールはこんな感じでした。
8:00~9:00 移動
9:00~11:30 一棟目の調査
11:30~14:00 昼休憩と移動
14:00~16:30 二棟目の調査
16:30~17:30 移動
17:30~19:30 宿で調査票作成
19:30~21:00 晩飯と風呂
21:00~23:00 調査票作成
23:00~就寝
これが3セット。
なかなかハードでしょ。
とにかく調査票の作成が時間かかった。持ち主の方にヒアリングを行い、その情報と目視での確認を元に調査項目を一つ一つ埋めていって、屋根裏も床下も覗いて、屋内外の写真を何十枚も撮って、その場所と方角とメモを記入して、図面を作成する。
とかやってると、一日で2棟が限界でした。
それを4万棟近い被災家屋すべてに行うにはいったいどれくらいの歳月が必要なのか。公費解体は進んでいるが、それが果たしてどれほど妥当な判断なのか。
一年以上経った今も、ほんとに問題は山積みです。
でもこうして一つずつやってくしかないのです。

一棟目の調査。
ツーマンセルでタッグを組んだ一級建築士の方が屋根裏をチェック。
これはこのお家に限ったことではないんですが、なんか能登の家はほぼすべてに布基礎がついてて、一見して伝統構法(石場建て)かどうか分からないケースが多発しました。
雪深いところだから、床下に雪が入り込むのを防ぐ目的もあったかもしれません。
とにかく全部に布基礎っぽいコンクリートが回ってるので、それが緊結されてるのか、ただコンクリの壁を造っただけなのかがぱっと見で分かんないんですよ。
この家もそれがあった上に、小屋裏にはかすがいが使われてたりして、でも巨大な差鴨居があったりして、うーん、これは…伝統構法なのか……? みたいな感じでした。
でも聞いてみたら築年数が1951年以前だったので、伝統構法だと判断しましたけども。
そういうのもまた日本家屋の地域性なんだろうと思います。


で、こういうダメージのある部分をチェックしていくわけです(掲載許可は頂いてます)。
土壁は崩れて、梁は浮いて止まっている。
ビジュアル的に、あからさまにダメージ感のある状態が直せずにずっとこのままあるというのは、本当に心理的にしんどいことだと思います。
僕も自分の古民家を一年かけて直した時に、とにかくボロボロ・ぐちゃぐちゃの家を何ヶ月も毎日毎日見せられることがほんとに辛かったし、何より自分の食器でメシを食えないこと、自分の時計で時間を確認できないこと、そういったことがとても辛かった。
自分で家を壊した僕でさえそうなんだから、ある日突然そんな暮らしを強いられることになった住民の方々の苦しさは筆舌に尽くしがたいと思います。

こちらは二棟目のお家。
この家も立派な古民家なんですが、屋根の荷重を受け、柱が地面に沈み込み、その際に破断したものと見られます。
翌日以降は現代の家も調査したんですが、古民家はこうしたダメージがすぐに目で見て分かるので非常に良いなと改めて思いました。
だって現代の家って大壁で柱や構造材がぜんぶ中に隠れてて見えないんですよ。だからどの部分がどうなってるのか、柱が折れてないか、金物が割れていないか、そういうのは天井や壁や床を剥がしてみないと分からない。つまり、「簡易調査不能」となってしまうわけです。
そういう点で、やっぱ古民家の意匠はデザイン的にも実用的にも優れているのだなあと痛感しました。
昔の人はさすがですね。
古民家が地震に弱いのか、強いのか、という話は次回にちゃんと語りますが、この二棟に関して言えば、よく持ちこたえているなと感じました。
土壁が壊れるのも、瓦がずり落ちるのも、柱が傾くのも、すべては柔構造の「何とかごまかしてやり過ごす」という設計思想からくるものです。
土壁は壊れながら揺れを吸収し、瓦は落ちながら頭を軽くさせ、一本の柱が折れても他の柱がそれを分散して補う。
金物を使わない木組の家は、揺れますが、揺れて曲がったあとは元に戻ると言われています。
そういう「柔」の感じはこの二棟からも充分感じることができました。
でね、調査を終えて家に帰ってきた僕は、土間のソファに座りながら、ぼんやりと調査の写真を見返していました。
倒壊は免れたとはいえ、縦に割れている柱を取り替えるのは大変だろうな、壁も直さないといけないし、ずれた梁なんか直すのにいくらかかるんだろうか……
そんなことを土間の天井を見上げながら考えていた時(長年のクロニカ読者様ならここで察してくれるよね)、僕の両目に信じられないものが飛び込んできたのです……

うちの梁もずれてた……………………

柱も割れてた…………………………(これ背割りじゃないの笑う)

土壁も崩れてた…………………(屋外10年放置)
ということでですね、
古民家に関しては「ダメージ」というのがなんというか、モヤッとしてるというか、フワッとしてるというか、なんかそういうもんなんですよ。
自然物に「ダメージ」っていう概念あんまり無いでしょ?
だからといって何でもいいってわけじゃないですけど、アウト/セーフの線引きが曖昧で、「まあこれくらいならいいか……」みたいな感じで暮らしていけるわけです。
それってすごくナチュラルな思考だと思いません?
クロスが破れてるからクロス屋を呼んで修理しないとダメです、床が汚れてきたからメンテナンスしないとダメです、そんなアウト/セーフの線引きって、いったい誰がいつ決めたんでしょうか。
なんかそういうのってちょっと息苦しい。
と僕なんか思っちゃいます。
新建材は明確に寿命があるからアウトのラインは守った方がいいし、現代の在来工法もきっちり計算されて造られてるからアウトのラインに細かい段階がある。
でも古民家に関しては、なんかそういうのはぼんやりと、なんとなく、ある程度までは自分の気持ち次第でどうにでもなるよね……
と思うんですよ。
住めるっちゃ住める。危険っちゃ危険。みたいな。
そういうところも、僕が古民家を好きな理由の一つです。
さて次回は地震というものについて、僕が能登半島を走破した経験から語ってみます。
乞うご期待。