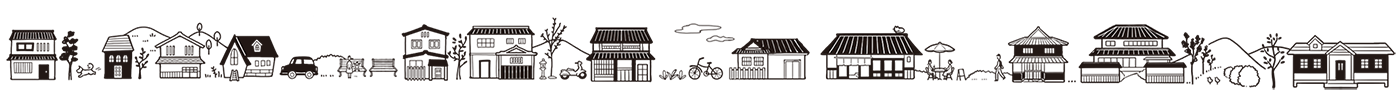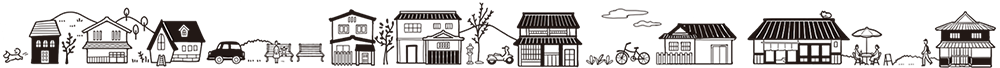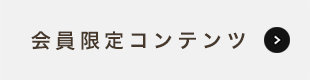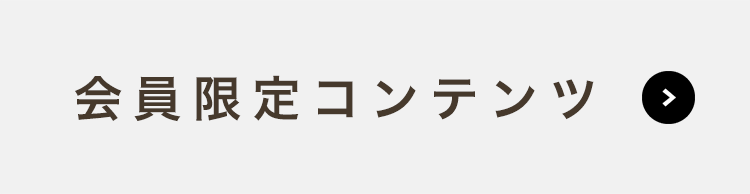能登半島地震レポート・その3
今回は能登半島地震レポート第三回です。
これまでの記事はこちら。
さて今回は「地震」というものについての総括になります。
住宅性能はいつでも計測・実験できるので細かく数値化されて語られるんですが、地震や台風などの天災はなかなかリアルタイムで計測したり実験したりできないので、よく分からないところが多い。
僕も地震コンテンツでいろんなプロの方々に地震について訊いて回りましたが、結局、結論としては「分からない」ということになるんですよ。
でもね、とは言え、もうちょっとなんかないのかと、この上↑のコンテンツ作ってから何年も経ってるわけで、もうちょっと新しい情報が欲しいなと思っていた矢先、今回の調査のお話が舞い込んできたわけです。
伝聞でいろんなお話を紹介してきたものの、やっぱり最後は自分で現場を見るしかないのですよ。
僕が見ても専門家のようなコメントは残せませんけど、何か感じるものがあるだろうし、現場で感じた雰囲気というのはプロだろうがアマだろうが、何か正解に近いのではないだろうか。
そう思って行ってきました。

これが三日間で僕が走ったルートです。
一番被害の大きかった輪島市や珠洲市を中心に、一日4~5時間かけてぐるぐる走ってました。
そうしていろんな景色を見た僕と、一緒に回った建築士の方が出した結論が、第一回目の記事でもお伝えしたように、
【運】
と
【地盤】
だったのです。
今まで地震の現場を見てきたいろんな人に話を伺ってきましたが、皆さん口を揃えて「古民家とか新築とかじゃない」「古民家は弱いとか強いとかそういう話じゃない」と仰っていた理由がようやく分かりました。
これは当たり前っちゃ当たり前なんですよ。
みんなそこにあんまり目が向いてないだけで、誰でも知ってる事実です。
でもこれは現地を車で走らなければ得られない感覚でした。
あのね、
輪島市、珠洲市、そこに建っていた家々が倒壊したんです。
逆を言えば、その近隣の市に建っていた家々は、ほとんど倒壊しなかったんです。
意味分かりますかね。
工法とかメーカーの信頼度とかじゃなくて、単純にその明暗を分かつものはまず何よりも「エリア」なんですよ。
つまり、運です。
順を追って見ていきましょう。

輪島市。
輪島市に至るまでの山道は第一回目で紹介した通り、あちこちが崩落していたんですが、人家はあんまりなかったんですよね。
その手前のエリアは車から見る限りそこまでダメージも見受けられず、じゃあ輪島ってどうなってるんだろうかと車を飛ばしたわけですが。
山を越えて輪島市に入った瞬間、景色が変わりました。
写真は焼失した「輪島朝市通り」の跡地。
ご覧の通り、既に全てが失われてしまったあとです。
これを見て伝統構法とか在来工法とか独自の耐震基準とか、そういうのが大事だと思えますか?
極論のように思えますけど、でもこれ、現実なんですよ。
僕の目の前にある現実。
震度7でめちゃくちゃになった家屋、どこからか出火、延焼、その果てがこの風景。
輪島市の周辺はそういうことにならなかった。
輪島市がそうなった。
まずここが一つの大きな話。運です。
運要素が大きすぎる。
交通事故は交通ルールをしっかり守ることでかなり回避できる。健康も食事や運動に気をつけていればリスクが減少する。
でも地震に対しての家屋は……
ということです。
だから地震対策として何よりも大事なのは、命を守る行動ですね。
頑丈な家づくりとかではなく、どうやって逃げるか、ということだと思います。
もちろんRCのコンクリートブロックのような家があったら壊れずに焼けずに済んだでしょう。
そのように耐震に全振りするのもアリです。
が、普通の人は、自分が生きているうちに起きるか分からない震度7の地震の直撃に対してそこまでパラメータを振り切ることはできません。
なので、普通の家で、どうやって外に逃げるか。だと僕は思いました。

こちらは焼けなかった朝市通り。
一見無事に見えますが、ほとんどの建物が傾いていてもう住むことはできません。
鉄筋だろうがビルだろうが震度7の直撃を食らえばどうしようもない。
建物はどうせ死ぬ。あとは人間が死ぬか生き残るか、という違いです。

僕はこの破断を見た時に「ああ、意味ないのか」と思いました。
地面がここまで割れると石場建てだろうがベタ基礎だろうが意味ないです。

破断するだけではなく、ご覧のように隆起もする。
もうめちゃくちゃ。
土台となる地面が狂ってしまうんだから、家は当然歪むし、当然倒壊する。

輪島市では倒壊家屋がそのまま放置されているところも数え切れないほどありました。
復興なんてほとんど進んでいなかった。
ちなみに我々が歩いて外から見た限りにおいて、この真ん中の建物が倒壊して、その左右が倒壊していない理由は、分かりませんでした。
もしかすると腐朽があったのかもしれないし、地面の割け具合が酷かったのかもしれない。建物の元々のバランスが悪かったのかもしれない。あるいは、たまたまなのかもしれない。
何かもう、何が起きても分からない、全部偶然なんじゃないかと思うような感想を抱きました。
これは輪島市の話じゃないですが、別のエリアを調査した際、そのお宅はほとんどダメージが無く、ご主人が「食器棚のお皿も無事だったんですよ」と仰っていたのですが、そこから徒歩1分くらいの近所の家が全壊していました。
そのご主人のお宅が超絶耐震設計だったというわけではないんです。普通の古家です。そして全壊したお家も同じくらいの築年数の、同じような家だということでした。
だから一つ目の大きな結論としては、
どんな性質の地震が、どこに発生するのか、その時に地盤がどう作用するのか、これが分からないんだから基本的にはどうしようもない、ということです。
古民家Loverの皆さんのためにお伝えしておくと、いろんなお話を聞く中で、古民家だった実家が残って、そうではない普通の家が倒壊した、という話も2つほど耳にしましたし、建具が「く」の字に折れ曲がるほどの地震を受けながら建物自体は無事に建っている古民家も調査しました。
なので「古民家は危ない!」「耐震性ゼロ!」といういつものアレはやっぱりガセなんだなと改めて思った次第ですが、さりとて、古民家だから安全!とも全然言えない、というのが現実なんだろうと思います。
長くなってしまった…
この辺で区切って、珠洲市の紹介は次回に持ち越します。
ひたすら落ち込むような内容の今回の記事でしたが、最後に一つだけ添えておくと、現地でお会いした地元の方々はほんとに皆さん前を向いて、僕らに明るく接してくださいました。
街を復興させるのはいつだって人間。
人間が前を向いている限り、街は何度でも甦る。そう思います。
つづく。