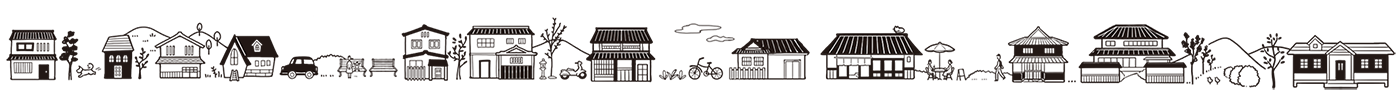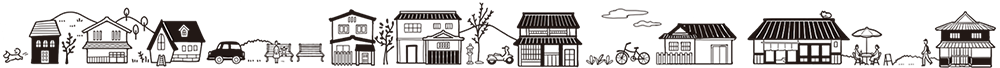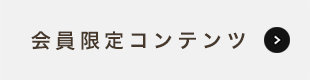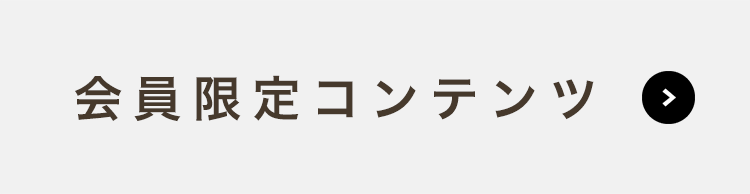落ち着ける家とはこういう家だ
今回は仮説論文回です。
古民家の選び方とか古民家の雑草対策とかではなく、単純に僕が考えていることのお話です。
古民家の実用的な話については過去記事にたぶん色々書いてるので、ブログのめっちゃ下にある(PCなら右カラムの一番上にある)検索窓で「選び方」とか「雑草」とかで検索かけてみてください。
さて本題。
いや先日ね、なんか和洋折衷の家のお客様とそういう話になって。
「落ち着く家」ってよく言うけど、それってどういうことなんだろうと。
実際、古民家はめちゃくちゃ落ち着くわけです。
朝でも夜でも、晴れていても雨が降っていても、食事をしているすぐ隣で子供たちがパンツを脱いでポークビッツを晒していても、どんな技を使っているのかそのポークビッツが両手で見たこともない形状に変形させられてて思わず二度見しても、いつも落ち着いて食事ができるんです。
なぜ落ち着けるのか。
それにはいくつかの理由があります。
たとえばデザイン。建具の高さと天井の高さ、窓の広さ、日本人が突き詰めた、そういった空間の黄金比。
あるいは自然素材ゆえに気を遣わない暮らし。傷が付いても、汚れても、へこんでも、新建材のように気にならない、経年変化を楽しみながら、リラックスして過ごせる生活空間。
古民家が落ち着ける理由としてはそれらも充分に正解だと思いますが、僕はもう一つ、常々感じていることがあります。
それは素材のこと。
ビニールクロスではなく自然素材の土壁、漆喰、そして無垢の柱がそのまま表に露出する真壁工法により、視界に常に「本物の木材」が入るということ。
それはべつに普段は意識してません。柱をじっと見るわけでもないし、漆喰に手で触れるわけでもない。
けれどその細部の素材感というのは、脳内の無意識下に働き続けているのだと思います。
そうして人の「やすらぎ」ポイントが少しずつ加算されて、ある閾値を超えた時に「この家って落ち着くよね」という感想が口から漏れるのだと。
よく言われるのは、自然素材、特に「木」とか「緑」といった要素に対して、人間の脳がいい感じに反応するということ。
それもそのはず、人間の脳というのは実は、狩猟時代からほとんど変わっていないのです(『スマホ脳』っていう本に書いてたよ!)。
文明が発生してから4000年くらいでは、人間の本能は変わらない。
つまりどういうことかというと、狩猟時代、死ぬか生きるかのデッドオアアライブな人々にとって、「木」や「緑」=「森」というのは、身を隠す場所であり、食物が手に入る場所であり、すなわち最&高のエリアだった。
だから現代の我々も、古民家で木や緑をたくさん見ると「落ち着く~」って感じる……のではないか!
これ。この説。
これはスマホ脳じゃなくて僕のオリジナル説ですが、たぶん当たってると思う。
であれば、実は皆さんの自然素材の家を愛し、無垢の木を使い、観葉植物を置こうとするその気持ちが、実は「おしゃれな部屋にしたい」や「癒やされたい」という欲求ではなく、
「死にたくない」
という壮絶な本能からくる欲求だということになります。
すごいよね自然界。
それと同じ理由で、「暗い」「狭い」というのも落ち着くポイント。
面堂終太郎 (を知らない方が既に世の大半であるという辛い事実を無視して書く)のように閉所恐怖症の方はいますが、基本的には明るくて広いのは、カッコいいとか、美しいとか、そういう感覚はあっても「落ち着く」とはなりませんよね。
やっぱりちょっと照明が暗くて、適度に狭くて、なんかそういうバーの方がなんかそういう感じになるじゃないですか。
僕お酒飲めないから知らんけど。
ともかく、いい感じに薄暗く、いい感じに狭い、それはつまり! 洞窟ってことですよ!
やっぱり身の安全基準!!
なので薄暗く、障子を閉めれば四畳半~八畳間という適度に狭い個室になる、という古民家はまさに人間の本能に最適化された空間だと言えるでしょう。
日本に限らず、伝統的な建物というものは、デザイン、構造、素材、そのすべてに何かしらの必然性があるものです。
なぜならそれは1000年2000年かけて少しずつ修正され、膨大な取捨選択が蓄積されたものだから。
そんな蓄積の前には、デザイナーの思いつきみたいなレベルのアイデアはとても生き残れず、みんなが「良い」と感じたものだけが建物に採り入れられ、残されていくわけです。
そうして完成されたものが、今我々が見ている「古民家」と呼ばれる建築物の正体です。
自然を神と崇め、自然に敵対するのではなく、自然と共に生きることを選んだ我々日本人が、限りなく自然環境に近い「古民家」という住居を生み出したことは、僕はとても納得がいくなあと思いますよ。
そういうわけで今回は「落ち着ける家」について語ってみました。
皆さんもぜひ古民家を買って、この弱肉強食の世の中をなんとか生き延びましょう!(違う)