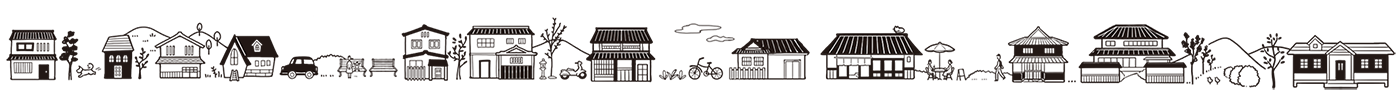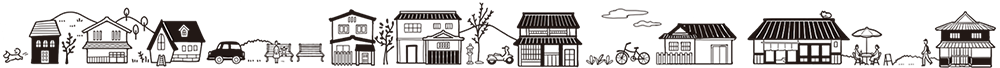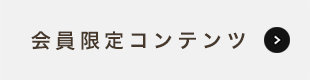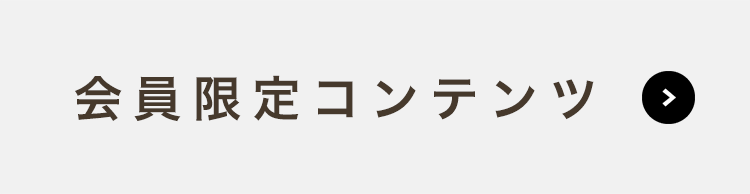僕はどうやって古民家をリノベしたか・その2「そもそも古民家って何?」
不定期でお届けする、もうこれは何度も書いたから今さら書かなくてもええやろ、という内容を新規読者様のために改めて書いていくシリーズ、「僕はどうやって古民家をリノベしたか」第二弾です。
説明が長い。
今回は「そもそも古民家って何?」という問題について説明していきます。
これはひょっとしたら何度も書いてないかも知れない。
前回、世界の真実の目覚めによって古民家を選んだ僕ですが、選んだ土地をキャンセルし、描いてた新築プランの間取り図を放り投げたあと、じゃあ今からどう動けばいいのか、がまったく分かりませんでした。
なぜ動けなかったのかというと、古民家に関する情報が無かったからです。
今でこそYouTubeとかSNSとかで古民家暮らしが発信されていますが、10年前の当時はそれすら無く、数少ない書籍を探したり、実際に古民家カフェをされてるオーナーに方法を聞いたり、ほぼ独学で勉強するしかないような状況でした。
その状況はのちに僕がクロニカを立ち上げる大きな要因となるのですが、とにかく何も知らない状態から出発した僕は、まず物件を探そうとして、わりとすぐに一つ目の壁にぶちあたりました。
というのも、調べて出てくる「古民家」が一種類ではなく、見た目も時代もばらばらだったからです。
その中には自分が思う「古民家」からかけ離れたものもありました。
え、これも古民家なの?
じゃあそもそも古民家って何?
結論から言うと、正確な定義って無いんですよね。
ほんとこの業界、あやふやなところや自称がまかり通ることが多い。
で、今なら僕は自分なりの「古民家」像を定義できます。
それは世間と一致しないかも知れないし、僕の好みが反映されたものでもあるので、あくまでこれはクロニカ的古民家像なんですが、僕の定義する「古民家」というのは下記のいずれかの条件を満たすものである。
- コンクリート基礎が無い
- 伝統構法である
- 建築当時にアルミサッシが使われていない
- 建築当時の棟梁がねじりはちまきである
- 建築当時の施主が全員和服
- まっくろくろすけが視認できる
このうち後半は無視でOKなんですが、まあ、基準にするべきは構造だろうと。
構造に関しては僕は最近まで1951年の建築基準法の施行前か後かで分けられると単純に思ってたんですが、最近、なーんかその辺りが混ざってることを知りました。
実際お会いする工務店さんや建築士さんに「古民家の定義は?」って訊くんですけど皆さんわりとバラバラだったりして、特に1950~70年あたりの建物の構造が複数パターンあってややこしい。
だからはっきり言えるのは、戦前なら古民家。ということです。
戦前の建物なら基礎は無いし、在来工法じゃなくて伝統構法だし、アルミサッシも使われておらず、棟梁がねじりはちまき、施主も和装でネコバス通勤でしょう。
なので今は2025年、終戦が1945なので、ようするに築80年以上の建物に関しては確実であると。
(ちなみに全国古民家再生協会さんの定義はまたちょっと違います)
でも不動産屋さんや一般の方などはこういう定義がないので「なんか古い和風の家」=「古民家」、と捉えがちです。
以前にも書きましたが、特に能登地震などで倒壊したとされる「古民家」の多くは伝統構法ではなく在来工法で建てられた「古い和風の家」だった、というのが僕の認識です。
また空き家バンクで「築52年の古民家!」とかよく書いていますがああいうのも僕の古民家観から外れます。
それはアルミサッシのついた在来工法の古家だろう、ということです。
繰り返しますがこれは僕の古民家観であって絶対的な基準ではなく、しかも好みの話です。
というか僕は築52年の古家、すなわち細い銀色のアルミサッシ、タイル張りのお風呂とトイレ、軋む階段やラワンベニヤの風味、という世界も好きだったりします。
だからこれは僕の中で「古民家とは何か」をどう定義づけているか、というただそれだけの話なのです。
とはいえ、物件探しにはそういう物差しは必要。
不動産屋さんに対しても、自分がどういう物件を欲しがっているのかを明確に伝える必要があります。
そんな時にこの記事を思い出して、自分の求めている建物が何なのかを見極めて頂けると幸いです。
で、
いろんな家を見に行ったり、いろんな本や雑誌を読んだりして、ようやく自分の探している「古民家」がどういったものなのかをざっくり把握した僕でしたが…
次は物件が見つからねえのよ。
だって「古民家」って市場が無かったから。
ということで、この話はまた次回。